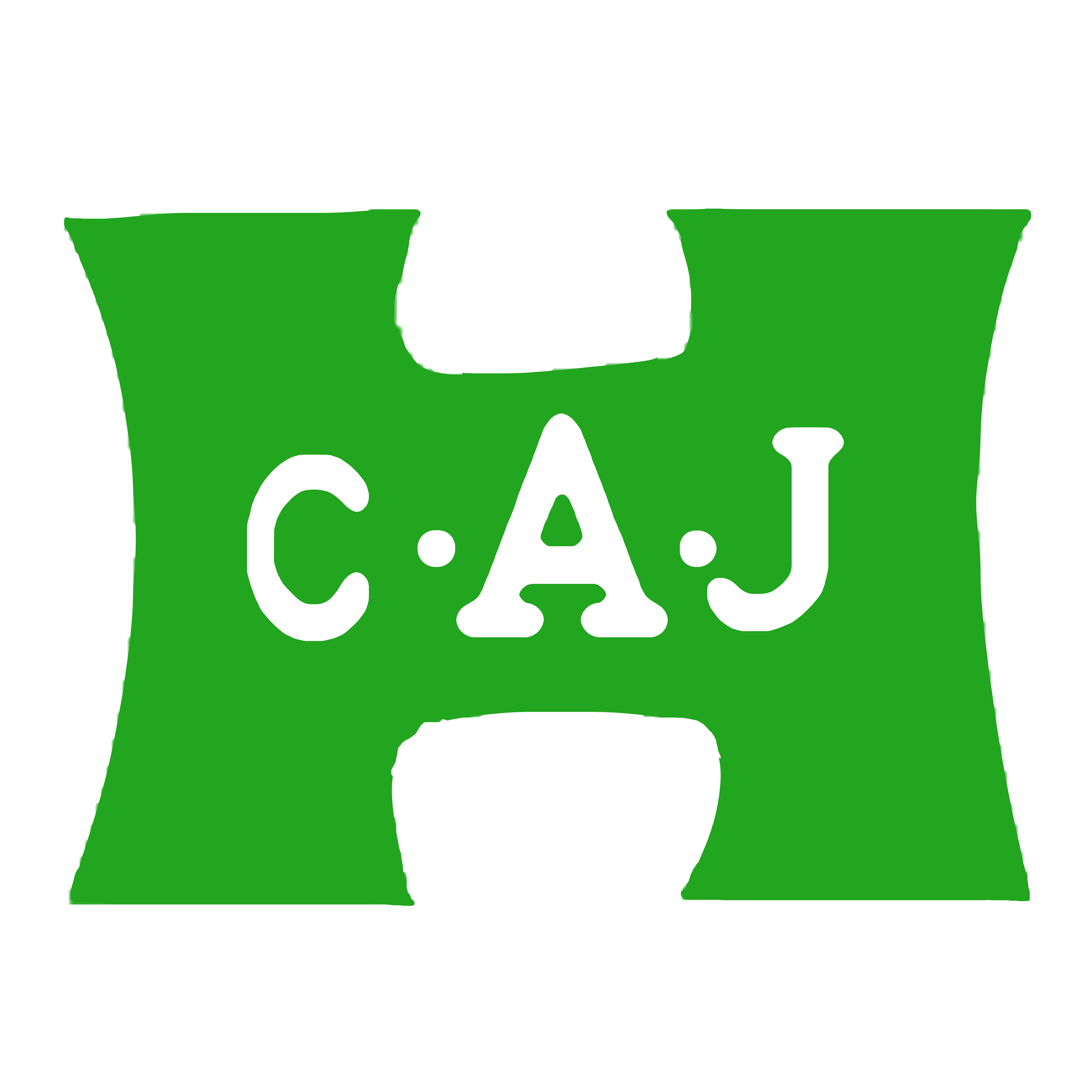平成24年01月01日
| 平成24年01月01日 ~あれから9ヶ月~ 「昨今の取り組み」~宮城県農業高等学校~ | |
| 昨年3月11日、突然襲った東日本大震災と大津波、そして東京電力原発事故と、日本の歴史において過去に無い大惨事が発生しました。発生から9ヶ月が経過し、少しずつではありますが復興・復活の道を力強く歩み始めた被災地の一つ、「宮城県農業高等学校」の様子を柳渕拓伸教諭に紹介して頂きました。 | |
| 震災前の学校 | |
| 本校は今年度で創立126年になる日本最古の農業高校で、創立当初(1885年明治18年)は仙台市太白区にて宮城県農学校としてスタート。77年に仙台平野の海岸から1㌔、仙台空港の北2㌔に位置する現在の名取市に移転しました。 学科は農業・園芸科、生活科、食品化学科、農業機械科の4学科を設置し、現在689名の生徒が在籍しています。 校訓である「自啓」(自らの道を自らで切り開く)を教育目標として、農業に関する知識、技術、技能を習得させ、豊かな人格の形成と生きる力の育成を図り、将来地域社会を担う有為な社会人の育成を目指しています。 更には自啓寮と呼ばれる寮も併設され、寮生活を通して様々なことを学んでいます。 | |
| 畜産部門について | |
| 本校の農業・園芸科では作物、野菜、草花、造園、果樹、バイオなど計9つの専攻があり、畜産もその内の1つです。 生徒は2学年時から希望選択で部門を専攻で、現在畜産部門では2年生13名、3年生16名の計29名が在籍しています。ほとんどの生徒が非農家ながらも、2年時には養豚、養鶏、3年時には酪農の実践的な授業を通して学習に対し、意欲的に取り組んでいます。 飼養牛は経産牛14頭、育成牛18頭、和牛2頭の計34頭。飼料畑4.2㌶にデントコーン及びソルゴーの混播を作付けし、収穫後は春穫りのイタリアンライグラス、また沿岸部で砂地の土壌であるので浸食対策と緑肥利用のためにライ麦を栽培していました。 平成21年度より体格審査と牛群検定を実施し、牛群の把握と改良の参考としながら、飼養管理と乳質改善、種雄牛の選抜に活用しています。その甲斐あって、牛群の繁殖成績は県下でもトップクラスになり、22年秋の審査では5産88点と評価される牛もでてきました。 参加当初は牛群レベルに加え、生徒教員共々、経験と指導力不足で結果を出すことが出来ずにいましたが、牛群改良が進み、さらには生徒自身の継続した取り組みが年を重ねる毎に結果にも表れ、県内共進会での上位入賞をはじめ、一昨年には東日本デイリーショーに初出品ながら2部1等賞4席に輝きました。 そして自ずと全日本ホルスタイン共進会への出場という目標が生まれ、生徒教員共に一丸となって日々の管理に取り組んでいましたが、口蹄疫の影響もあってその目標は果たせなかったものの、共進会出場に向けた取り組みは生徒の学習への姿勢に大きな変化をもたらしました。 | |
| 震災当日の様子 | |
そのような活動をしていた中、14時46分大きな地震が発生し、さらに1時間後に10mの大津波が襲って来ました。幸い、地震発生後すぐに校舎屋上に避難していたいので全員無事でした。 黒い大きな壁のような濁流に全てが飲まれていく様子を見ているなか、2人の酪農担当職員が「牛を逃がしに戻った」という事実を聞き、大きな絶望感を感じました。すでに校舎の周りは全て海に変わってしまい、校舎より低い建物はほとんど飲み込まれ、最悪の結果が頭をよぎりました。夜になり2人からの「無事だ」との声を聞き、全身の力が抜けたのを覚えています。 興奮し、なかなか言うことを聞かない牛を苦労して逃がした直後に津波が来て、慌てて近くにあった鉄塔によじ登り難を逃れたとのことでした。 その日は一晩学校に待機し、余震が続く中、不安で眠れぬ夜を過ごしました。助かった職員の2人は鉄塔がある丘の上で流れ着いた動物たちと一緒に夜を過ごしました。 学校から5㎞以上も流された牛もいたのですが、周辺住民の方々に保護して頂きました。多くの方々に命を繋いでいただいたことをとても感謝しています。 | |
| 震災後について | |
| 津波によって学校のすべての施設が使用不可能となり、本校は宮城県内の三つの高校(加美農業高校、亘理高校、柴田農林高校)に分散しての授業が再開となりました。 なかでも、加美農業高校組では、登校中のバスの中でも事業を実施するなど、生徒も教員も多くの不安を抱えたなかでの再開でしたが、三校の協力もあり、授業を継続することができました。 生き残った牛達は、加美農業高校と柴田農林高校、宮城県畜産試験場にお世話になり、命を繋いでいただきました。 | |
| 奇跡の牛と共に | |
| 分散して通っている学校と違う場所で飼養されている愛牛に、一日も早く会いたいという畜産専攻生の希望もあって、休みなどを利用し、管理に行かせました。震災以来に再会した生徒はとても嬉しそうで、牛達への深い愛情を感じました。 そのような中、23年度初めてとなる宮城県同志会ホルスタイン共進会の開催が決定し、自ずとこの生き残った牛達で出場したいとの声があがり、出品へ向けて取り組むこととなりました。 共進会までの間、生徒達自身で管理・調教のローテーションを決め、週末を中心に加美農高に預かっていただいている牛達の管理・調教をしながら本番に備えました。 結果は2部優秀賞4席、3部最優秀賞2席、4部最優秀賞2席と3頭すべてが入賞した上に、未経産の部でリザーブ・グランドチャンピオンに輝くことができ、本校初めての快挙に畜産専攻生全員の喜びは元より、何よりも震災後、津波の被害があった中での入賞でしたので学校、そして地域の方々にも希望を与える入賞となりました。 牛が戻ったことで、今までの活動も復活し、県内実業高校のイベントに併せて県庁の広場に牛を展示し、畜産のPR活動を行う事も出来ました。 | |
| 今後に向けて | |
| 正直に話せば、今後の畜産専攻の展望としてはまだ見えない部分が多々あり、不安が無いと言えば嘘になります。 ただ、今私達が出来ることは、生き残った牛達のDNAを残していくことと、これまでと同じ意識を持って改良を進め、生徒に良い教材となるような牛、更には全日本共進会へ出場出来るような優良牛を生産したいと考えています。 本校は被災を受けましたが、思いは変わらず、強い心で学習に取り組んでいます。今後も様々な困難や不都合な部分は生じると思いますが、そこにとらわれてばかりいては前には進めないので、教員、生徒一枚岩となって困難を乗り越え、学習に取り組んでいきたいと考えています。 | |
| (文・柳渕拓伸教諭) | |